VOL.51
増田惠子 氏×山本一郎
ピンク・レディーから増田惠子へ。出会いはいつまでもつながっていく
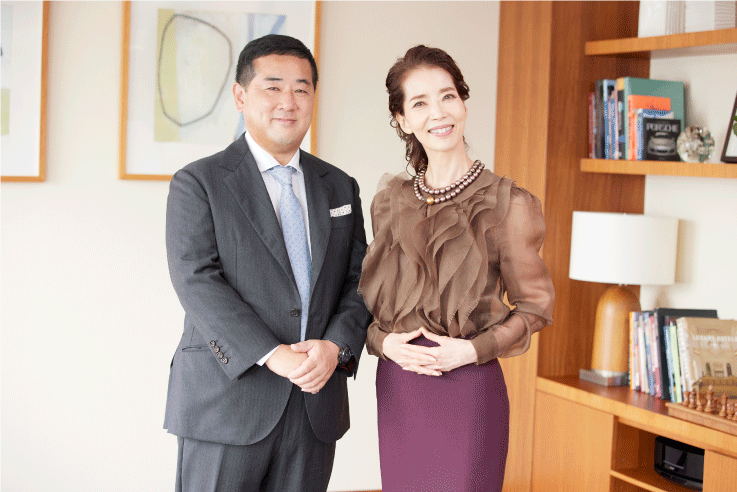
対談相手のご紹介

歌手・女優
増田 惠子
Keiko Masuda
歌手・女優。1957年9月2日生まれ、静岡県出身。O型。1976年にピンク・レディーとして「ペッパー警部」をリリースしデビュー。その後「渚のシンドバッド」でミリオン・セラーを記録、「UFO」「サウスポー」「カメレオン・アーミー」など、数々のヒット曲を世に送り出し、社会現象にもなった。1981年に解散後、「すずめ」でソロデビュー。1982年に「すずめ」が40万枚のヒットを記録、その後映画・舞台・テレビドラマで女優としても活躍を開始する。2010年に“解散ヤメ!”を発表し、ピンク・レディーが再始動。アルバムを発売し、全国ツアーを行う。2022年9月2日にソロデビュー40周年記念&バースデーライブを成功させた。
2022年7月27日(水)よりソロデビュー40周年記念アルバムが好評発売中!
増田惠子 / そして、ここから... [40th Anniversary Platinum Album]


2022年12月25日(日)増田惠子Christmas Dinner Show「そして、ここから・・・」東京會舘にて開催決定!
東京會舘の公式サイトはこちらから
https://ap.kaikan.co.jp/news/20220920_003630.html
◆お問い合せ先
TEL:03-3215-2111(代) MAIL:event@kaikan.co.jp
対談の様子
山本:私はピンク・レディーの大ファンで、いまでもポスターやレコードを大切に持っていて、本日はそれをお持ちしました。10代の頃に小遣いを貯めて買ったものです。
(ポスターやレコードを見せて)このポスターは下に会社名が入っていますから、当時はこの会社の商品を買って応募したのが当たったものだと思います。それくらいピンク・レディーの大ファンでしたので、増田氏惠子さんにお会いできて光栄です。
増田氏:ありがとうございます。どれもその時のことを覚えています。どこで撮影して、どんな衣装を着たかまではっきり。
本当に長い間ファンでいらっしゃる方が多く、感謝しています。デビューが1976年ですから、今年で46年目、ソロ活動を始めて40年になりました。こんなに長くお仕事をできるとは思っていなかったのですが、いまはますます歌うことが面白くて仕方がありません。やはり年を重ねたことで、歌詞に対して自分の受け取り方が変わってきたからかもしれません。
若い時には若い時なりの歌詞の理解力で歌っていましたが、60歳を過ぎると歌詞の深さが自分の人生と積み重なって、同じ曲でも歌い方が変わったり、そこに込める思いも変わったりします。歌には100点満点はないし、これが正解というのもない。すごく奥の深い面白いものだとつくづく感じます。
山本:同じ歌うということでもますます深みを増していく。
いまのお話で感じることは、私の仕事でも同じことが言えます。私たちも常に開発をしていくのですが、100点は絶対に取れないんですね。毎回、「ここがダメだったな。ここもこうしていたらよかったな」という部分が生まれます。ですから、ずっと開発し続ける。歌うことと私たちが開発することは、よりよいものをつくるという意味では同じかもしれません。
私がスタッフたちによく言うのは、「『創造』の『創』を考えなさい」ということです。「造」という言葉をあえて捨てることで、人がつくらないものをつくり上げようと言っています。すると、お金がない時に苦労してつくったもののほうが、のちのちになって「ああ、よかったな」というものが生まれたりするんですね。
増田氏:たしかにお金も大事なのかもしれませんが、何かをつくり上げるという作業には、深い部分に「愛」が必要なのだと思います。
最近、そのことを強く感じた出来事がありました。ソロデビュー40周年ということで、古巣のビクターから7月27日にアルバムを出していただきましたが、WOWOWプラス歌謡ポップスチャンネルで「増田惠子ソロ40周年記念ドキュメンタリー『そして、ここから・・・』」という番組を放映するということで、去年の11月から今年の3月くらいまでずっと追いかけてくださいました。
その間、どこに行くにも一緒についてきてくれたのですが、2月から3月にかけて行われたレコーディングにも同席されました。ただ、私にとってはレコーディングのスタジオというのは神聖な場所ですから、そこは自分しかいない。それが当たり前でしたし、カメラを意識しなければいけないという状況はできるだけ取り払いたいと思っていました。
そうやって仕事をしてきたのですが、カメラマンがスタジオのブースの中に入るということが初めてで、最初はかなりきついなと思っていたんです。でも、私の40周年アルバムの記念ドキュメンタリーですから、やはりレコーディングの映像も必要だということも理解していました。
そんな思いを察してくれたのか、別のいい方法はないか皆さんが考えてくれて、定点カメラで撮影していただきました。定点カメラなら人がいなくても撮れるというので、カメラに狙われている感覚と闘いながらも撮影を終えることができました。また、配信ライブもやったのですが、そうした一連の風景もあったりして、私の活動すべてのドキュメンタリーの映像ができました。

そうしたモノづくりに愛を感じたのは、映像にナレーションを入れていく編集作業の時です。もちろんナレーションはプロの方が入れるのですが、その前段階で、番組のディレクターさんがナレーション原稿を読んでいる映像をチェックしたんですね。やはり言葉が入ってくると、自分が思っていたよりもとても素敵なドキュメンタリーになったなと思ったのですが、その後、プロの方が読んだ本番の放送で使用する映像を最終チェックした時に、「あれっ、何か違う」と思ったんです。
プロの方のナレーションはものすごく流暢で上手なのですが、あの編集作業の際にディレクターさんが読んでくれた時のほうが、たどたどしいんですが、愛があると感じたんです。それは、ずっと一緒に何カ月も過ごしてきて、私の人となりをよくわかってくださっていて、私に対しての愛もいっぱいある。そういう方がナレーション原稿読んでいると、その愛がナレーションの声と共に流れてくるんです。愛ってこういうことなんだな、人って愛なんだなと、一緒につくるという経験を通して感じました。
山本:とてもいい話です。創造の「創」の中には、たしかに愛があって、愛があるからこそ素晴らしいものが生まれる。
ドキュメンタリー映像も単にその人の日常を照らすだけでは“つくる”で終わってしまうものが、そこに愛が加わることで観る人にも感動を与える。
今回の増田さんのアルバムもそうした愛がたくさん込められているのではないでしょうか。
増田氏:ドキュメント映像を撮っている時には、アルバムが『ここから』というタイトルだったんです。プロデューサーさんからも「ここから、ケイちゃんが一から頑張る」という感じで、カメラも同じように私を追っていたのですが、ある時、私は少し違和感を覚えました。
18歳で静岡から東京に出てきてこの仕事を始めて、大好きな歌を歌えた喜びと一緒に、たった5年間でしたが大変な時代、壮絶な日々を生きてきた思い、私のこれまで自分が選んできた道や紡いできた時間。そして、私と同じように一緒に時を過ごしてきてくれたファンの方たち。そうした45年という時があって、凛とした姿で清々しく、新しいもう一歩を生きていきたいという思いを感じたんです。ですから、「ここから」という言葉だけでは何か足りないなと。
そんな私の違和感に、音楽プロデューサーさんから、「ケイちゃん『そして、ここから・・・』っていうのはどうか」と提案をいただきました。その時に、私もしっくりいって、それがいいとアルバムのタイトルが生まれたんです。
「そして」という言葉は、これまでのものすべてを自分で抱きしめて、「ここから、また一歩」と歩んでいく。それはゼロから頑張るのではなく、過去もすべて優しく抱きとめながら一歩ずつ進んでいける……。
タイトルが変わったことで、また映像の撮り方も変わって、本番の放送の映像を見た時には、関わったスタッフ皆さんの愛が画面にキラキラして見えたんです。そんなことは初めてです。ですから、アルバムも私だけではなくたくさんの方たちの愛が詰まっていると思います。

今回のアルバム制作、ドキュメンタリー制作を通して、一番大事なのは人の思いや愛なんだということを思わずにはいられませんでした。実際に愛を感じると、これはもう間違いないって思った日から、何か人生がキラキラしてくるんですよね。ですから、人が1日1日を生きていくというのは、年を取って夫婦で過ごしている方も独りで暮らしている方も、たった1人で生きているわけじゃない。たとえば、八百屋のおじさんと会ったり、道ですれ違うご近所の人がいたり……。
人間という言葉は「人と人の間」と書くくらいですから、人とのつながり、人との出会いで生きている以上、人に向ける愛、思いやる気持ち、感謝といったものに支えられている。今のようなコロナがまだ終息しない時代であっても、そんなささやかな希望があるからこそ生きていける。そんなふうに思う自分になりましたね。
山本:私にとっての感謝の気持ちはピンク・レディーで、18歳の時からずっとたくさんのエネルギーをいただいてきました。それが糧になっていまだにファンの方もたくさんいらっしゃると思います。
そんな増田さんの愛が詰まったお話を伺いましたが、ファンの方への愛も熱いと思います。
増田氏:そうですね、11年前、ミーと2人でコンサートをやった時にも、昔は小学生やもっと小さかった人たちが、大人になっても1曲目から皆さん総立ちで、みんなの目が子供に戻っている。そんな景色をステージから見られる幸福感というか、誰もがなかなか経験できることではないと思うと同時に、これまで元気でやってきたからこそ見られたご褒美ではなかったかと思うと、感謝しかないですね。
ここ10年以上コンサートをやっていませんが、あの時の会場の皆さんのキラキラする様子や、心の中にピンク・レディーって生きているんだなと思うと、それがまた励みになって、ファンの方々の思いにずっと応えていけたらいいなというふうに思っています。
ピンク・レディーという存在は私自身の礎みたいなもので、4年7カ月の活動という経験から人との出会いが今の私をつくっているとあらためて感じます。そして、絶対に諦めないということと、人はその気になったら何でもできるという信念のようなものを強く持つことができた時間でした。だから、1981年に一度解散してから、11年前に「解散をやめて、死ぬまでピンク・レディーです」と宣言させていただいたんです。
人間やる気になったら何でもできるっていうことを教えていただいてから、ソロになってからも辛いなとか、無理だなと思ったことは一度もありません。比べるものがあまりにもハードルが高いと思いますが、たとえば、少し体調が悪いなと思っても、「あのときに比べたら何でもない」と、いい意味で諦めないという気持ちを持ち続けていますね。
山本:ピンク・レディー時代に入院されたことがありましたよね。あの時は私の母が心配して手紙を書きなさいというので、姉と弟の兄弟3人で手紙を書いたことがあります。そのあとで「この手紙、どうするの?」と聞いたら、「送るところがわからない」って(笑)。
ただ、母は「あんなに仕事をさせて」と怒っていたのを覚えています。諦めずに頑張っている増田さんの姿そのものです。
増田氏:あの時は無理をしすぎて、結果的に腹膜炎になってしまい入院するしかありませんでした。その2カ月くらい前からすごく背中が痛くて、マネージャーに「どうも背中が痛くて……」と伝えていたのですが、忙しくて疲れているだけだと励まされたんです。結局、その時に病院に行けばよかったのですが、気がついたらTBSのスタジオの前で倒れてしまって……。
我慢できず倒れてしまうほどにならないとわからなかったようで、すぐ病院に運ばれて、腹膜炎だからすぐ手術しないと死んでしまうくらいひどかったようです。でも、実は10日後に武道館での初めてのコンサートが控えていたので、「いまは手術は無理です」と先生にお願いしました。結局「手遅れになる」ということで手術をして、8日間くらい入院しました。
退院して前日のリハーサルをして、翌日は武道館のステージに立ちました。当時の手術では腹膜炎は縫うことができなくて、おなかを切ったままそこにガーゼを詰めて、衣装に染みるといけないのでラップを巻いてステージに立ったんです。いま思うとよくできたなと思いますが、すでにチケットも完売しているし、初めての武道館コンサートをキャンセルするなんてあり得ませんから、とにかくステージに立ちたいという思いだけでやり切りました。
院長先生には責任を持てないと怒られましたが、コンサート当日は婦長さんと一緒に現場に来てくださったんです。だから、そのステージに立てた喜びでガンガン歌って踊って、あの時ほど幸せだなと思ったことはありません。
山本:いま伺っても本当にすごい話です。ファンの方々へ応えようとする諦めない気持ち、そして人と人がずっとつながっていてお互いが幸せを感じる。
そんな増田さんの原点についてもうかがいたいと思います。増田さんはお父様を3歳の時に交通事故で亡くされたそうですが、どんな思いで頑張ってこられたのでしょうか。
 増田氏:あの時のことは、お葬式の日を含めてよく覚えています。父はきっと早く逝ってしまう運命だったからなのか、亡くなるまでの思い出も覚えています。たとえば、私が父の膝の上に座ってお刺身を食べている光景とか、私が嫌いだと言って口から出してしまったものを父が代わりに食べてくれたことなど、とても優しい父親でした。
増田氏:あの時のことは、お葬式の日を含めてよく覚えています。父はきっと早く逝ってしまう運命だったからなのか、亡くなるまでの思い出も覚えています。たとえば、私が父の膝の上に座ってお刺身を食べている光景とか、私が嫌いだと言って口から出してしまったものを父が代わりに食べてくれたことなど、とても優しい父親でした。
そんな父が亡くなった時は兄が9歳、姉が6歳。私は3歳と末っ子でしたので、働かなければならなくなった母も私の世話をする時間もなく、しかも当時は小さな子供を預かってくれるところもなかったので、母の姉である叔母夫婦のところに預けられることになりました。電車で30分のところではあったんですが、やはり母や兄弟と別れて生活するというのは、私自身それなりの覚悟はありました。
でも、叔父や叔母はとても優しくて、綺麗なお洋服もいっぱい買ってもらったり、家にもたくさんのお菓子が置いてあったりと寂しさを感じさせないようにしてくれました。母も私を土曜日に迎えに来てくれて日曜日にまた送っていくというように、私がなるべく兄弟のそばにいられる環境をつくってくれました。
きっと父が亡くなったのは運命でしょう。私は自分が亡くならない限り父とは会えないと思っていたので、その時に「けいこ、頑張って生きてきたね」と頭を撫でてもらえるように生きていきたい、ずっとそう思って生きてきました。だから、神様は今でも父なんですよね。
素敵な父でしたが、母も兄弟も叔母も本当のことを言うので、そういったことを聞いて育ったからこそ自分の置かれた状況というのがよくわかっていたのかもしれません。3歳の頃からいろいろなことを覚えているのは、すでに大人だったというか、自分に負けない生き方をしてきたのだと思います。
山本:もしお父さんが亡くなっていなかったら歌手になってなかったかもしれないですね。
親や周りの人の死というのは、残された人にお役目があって、たとえば家業を継ぐことなく別の道で大成功した人も多いそうです。
増田さんが歌手という道を歩んだのもそうしたお役目があったからなのかしれません。
増田氏:そうかもしれないですね。私も母や兄弟と別れて生活して自分の運命を受け入れたのかもしれません。いまは母も叔父・叔母も亡くなってしまいましたが、母と叔母は本当に仲の良い兄弟で、育ての母である叔母は、母が残してくれた血がつながっている兄弟だなとつくづく思います。
3歳から叔母夫婦に預けられて、のちに私は養女として籍を入れて増田姓になるのですが、叔父も早くに亡くなってしまいました。私が中学1年の時でしたから10年ほどしか一緒にいませんでした。
その時に、たまたま独り暮らしをしていた祖母の体の具合が悪く、叔母と私は祖母のところ、つまり母と叔母の実家ですが、そこに移り住みました。祖母の家は母の家から歩いて30分もかからないくらのところにあり、互いの家を行ったり来たりしていました。
私は物心ついたときから歌手になりたという夢があったのですが、母は応援してくれて叔母は恐い世界に出すなんてと反対でした。母は私に寂しい思いをさせたから娘の応援をしたいと思っていたでしょうし、実際に育てている叔母は心配してくれたのでしょう。2人はまったく別の考えを持っていたので、私のことで言い合いしたりしたことがありましたが、それでも応援してくれて東京に出してもらっていまの私があります。2人も亡くなって、いまはきっと天国で仲良くしてくれていると思います。
山本:増田さんは多くの方の愛情を受けながら自身の夢を叶えていったんですね。
お父様への思いが原点にあって、苦労しながらも応援し続けてくれたお母様、そして、増田さんを育ててくれた叔父様、叔母様。何かそれぞれの形で、増田さんのお役目であった歌手への道へ押し上げてくれた、そんな気がします。
増田氏:そうですね。父と母、叔父と叔母はそれぞれ違うお墓に入っていますが、実は2つのお墓は同じお寺にあって、お墓参りの際は一緒に供養しています。その時にいまの私があることに感謝の思いを伝えています。
昔はいろいろなことをお願いしていたのですが、最近、お墓はお願いするところではないと聞いて、いまさらながら、近況の報告と幸せにやっているから見守っていてくださいということを伝えています。
あとは、夫のご両親のお墓にも参っています。私は44歳で結婚しました。夫のお母様は結婚する前に亡くなられましたが、生前は私をものすごく可愛がってくれた、そんな方でした。というのも、夫の姉にあたる娘さんがいたそうですが早くに亡くなってしまって、その娘さんが私と同じ名前だったそうです。
そういったつながりがあったせいか、お母様は娘が帰ってきたという思いで、初めてお会いした時からとても可愛がってくださいました。だから、初めて夫の家のお墓参りに行った時に、私と同じ名前がお墓に刻まれていたのを見て、何ともいえない不思議な気持ちになったことがあります。何か縁というものに導かれていますね。
山本:お墓は亡くなった方をつなげてくれる大事な場所ですから。
お話を聞いて思うのは、やはりお墓参りに行くと綿々と続く縁を感じて心が洗われます。私たちの仕事もお墓を売ることだけではなく、いかにお墓参りに来てもらうかということです。お墓参りをする人たちを育てると言うとおこがましいですが、子供たちも楽しんで来てもらえるように霊園に電車を置いたりといった工夫をしています。
増田氏:それはいいですね。うちの家族は兄も姉も、お墓に行けばいつも父がいると思って、よく母の後ろについてお墓参りしていました。だから兄と姉は、結婚してからも子供たちを連れて「おじいちゃん、おばあちゃんのところへ行くよ」と、お墓参りをしています。
ですから、甥や姪もみんなお墓参り大好きですね。やはり親に連れられて行くと、それが1つの見本というか、それが習慣になっていきますね。そこに亡くなった人はいないのかもしれないけれど、何か心が洗われるような気持ちになります。
 山本:お墓参りのPRをしていただいているようでうれしい限りです。
山本:お墓参りのPRをしていただいているようでうれしい限りです。
実は日本人は、世界の中でも一番お墓参りをする民族です。しかも、お墓に食べ物を備えたりする習慣は、世界でも類を見ません。花やキャンドルを置くという国は多いのですが、アジアの国でも食べ物を置くというのは、まずありません。これは、日本人は先祖も残された子孫も共同で生きているという考え方があるからでしょう。
現在の真言宗の高野山でも、毎朝6時頃から弘法大師のために朝御飯を持って行ったりする習慣があります。こうした文化は日本だけで、私はいいことだと思っていますが、さすがに置いていかれると困るので持って帰ってもらっているそうです。そうした習慣までありますから、日本人は亡くなった方とのつながりは深いといえます。
増田氏:私の恩師である阿久悠先生が2007年に亡くなって、2、3年後してから私が住んでいる近くにお墓ができたんです。歩いても行けるくらいなので、阿久先生のお墓参りは毎年行っています。
今回もアルバムを持って「先生、できましたよ」とお見せしました。この時は阿久先生のマネージャーもしておられた音楽プロデューサーの方と一緒に行ったのですが、ご報告と感謝を申し上げてきました。でも、阿久先生には墓前でお願い事ばかりをしてしまいますね。
あとは、私のルーツである先生方でお墓参りに行けないところ、たとえば「スター誕生!」でプラカードを上げてくれた相馬さんの命日には必ず、奥様にカサブランカの花を送って、その夜にちょっと奥様とお電話で話しをするというようなことをしています。
山本:なかなかできることではないです。阿久悠さんもほかの先生方も喜んでいらっしゃるでしょうね。
阿久悠さんは、私が子供の頃に音楽番組の審査員席でちょっと気難しそうに座っていた、ちょっと怖そうな先生というイメージがありました。
増田氏:いまでも恐いですよ(笑)。だから、お墓の前に立つとちょっとピリッとしますね。
私が素人の時に出会った先生にはものすごく緊張しますよ。師弟関係は変わることはないですね。でも、亡くなったいまでも私を見守ってくれている気がします。いまの自分をつくってくれた方ですから、たぶん私は今でもつながっていたいんだと思います。
恩師の先生方と出会いピンク・レディーが生まれ、そこからファンの方々と出会い、今も皆さんとつながっている。私があちらの世界に行ったら、父だけではなく、多くの方々からも「よく頑張ったね」って言ってもらえるような人生をこれからも歩んでいきたいですね。
山本:人とのつながりをとても大切にしていらっしゃる増田さんですが、実は増田さんが書かれた『あこがれ』(注:2004年、幻冬舎刊)という本の最後に、こういうふうに書かれています。
「人生に偶然は存在しない。すべて必然だと信じている。人と人との巡り合い。この地球上に多くの人間が生きていて、選ばれて出会う。一生会わない人のほうが遥かに多い。そういった中でこの人との出逢いにはどんな意味があるのだろう。神様は私に何を伝えようとしているのか、教えようとしているのか、いつも考える」と。
増田氏:あっ、読んでいただいて思い出しました。これを書いたのは20年ぐらい前、ちょうど100カ所、200回公演のピンク・レディー復活コンサートの真っ最中で、全国を回りながらずっと書いていました。編集者の方に原稿を送ってはダメ出しをもらいながら、けっこう時間がかかったことをすごく覚えています。
そして、ドキッとしたんですが、本を書いた時から20年経って、最後に書いた部分、まさに自分自身への問いかけに対して、いまはちゃんと自分の中で答えがあるなと思ったんです。ですから、思いついて書いた言葉ではなかった。いまこうして笑顔で、出会う人出会う人を大事に、その瞬間を大切に生きているんだと思います。
あの時の答えを導き出した20年、これからももっともっと心を磨いて、本当の答えがはっきりと見えてくる最後が迎えられたらというふうに思っています。
山本:現在の増田さん、そして、それが形となった『そして、ここから』にはたくさんの思いが込められている、そんな貴重なお話をお聞かせいただいき、私も何よりの励みになりました。
本日は本当にありがとうございました。



