VOL.33
桂春之輔 氏×山本一郎
落語界に学ぶ、一族継承の団結力
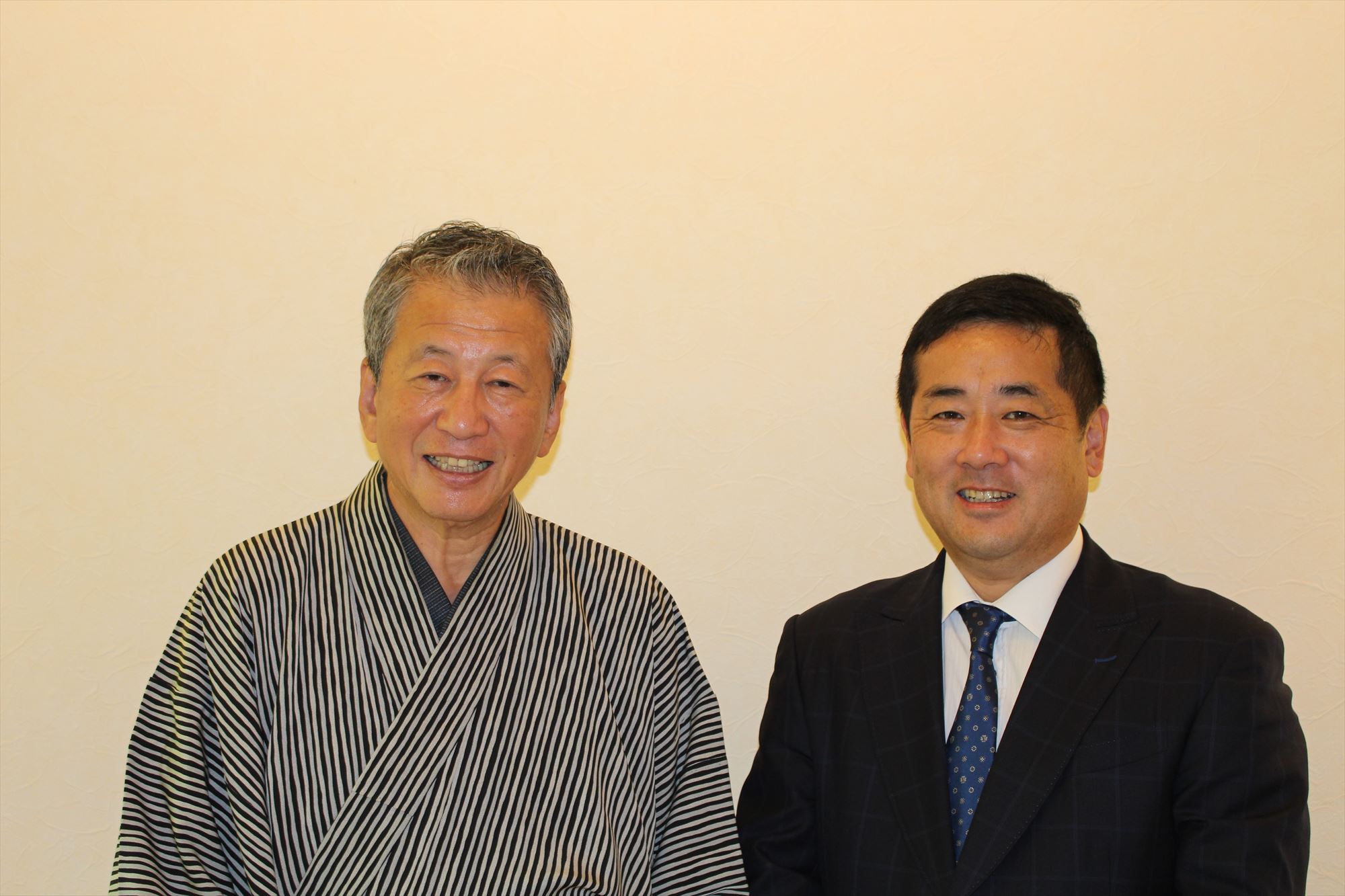
対談相手のご紹介

落語家
桂春之輔
harunosuke katsura
初舞台は昭和43年の新世界新花月。
昭和43年桂春之助に改名。テレビ番組「2時のワイドショー」では、ミヤコ蝶々から「はるさん」と愛称で呼ばれ可愛がられていた。桂三枝(現:六代桂文枝)の上方落語協会会長就任後、現在も同協会の副会長として一門、上方落語界の隆盛に力を注いでいる。
平成19年には、大阪市立大学において春團治一門が講演する授業「大阪落語への招待」に主任講師として招かれ学生とともに一般の方も聴講し、大阪落語への関心の高さを示した。
平成30年2月、四代目桂春団治を襲名
対談の様子
山本:弊社のこの企画は師匠で33人目になるんですよ。
春之輔氏:すごいですね。そうですか。それはどちらかというと堅い方々ばっかりなんですか?
山本:堅い方々・・・まあ。
春之輔氏:そりゃあ。もちろんお寺さんをはじめ、ひょっとしたら私が一番柔らかいほうかもわかりませんなぁ。
山本:ただ、落語の世界っていうのは伝統的なものですよね。
春之輔氏:そうです、はい。
山本:もともと歴史的にはどういうものなんですか。
春之輔氏:よく古典落語って言われるものがあるんです。僕はあまり古典という言い方が好きやないんですわ。で、歌舞伎や文楽と同じと言われますとね、それこそいわゆる大衆のものであって、あんまり芸術扱いにされるのは好ましくないと僕は思うんですよ。よく学校なんかで、中学や高校で、芸術鑑賞という形で、今言いました文楽や狂言のことを言わはるのはわかるんですけど、落語は違うやろ、と思うんですね。それはそれぞれの捉え方で、僕らやってる落語は決して芸術やおもてませんからね。そらもうそれぞれが思って、噺家の中には、俺らがやってるのは芸術だ。そう思ってる人がいるかもしれないですけど。それはそれでいいわけで。私自身の捉え方なんですけどね。
山本:ところで今度、四代目春団治さんを襲名されるんですね。
春之輔氏:それがね、師匠の遺言として、1年半前に伝えられたんですけれども、私が驚いたのは、想像以上に大きな名前なんですよね。今から20年以上も前でしょうか、高倉健さんにお会いした時に、健さんがおっしゃられたんですね、私は春団治の弟子です。と言うと、はぁ~、じゃあ落語のご先祖だ、と言ってくれたんですよ。春団治という名前は決して先祖ではないんですが、それだけ影響力がある名前といってもおかしくないんです。
山本:春団治さんは、歌にもあります、破天荒というか型破りというかそういう人物ですよね。
 春之輔氏:そうそう。それで、初代春団治がなんせ型破りな方でして。で、二代目が大変苦労をされたんです。それから私の師匠の三代目は、初代とは人生観も落語そのものも180度違う人でしたよね。おっしゃられる通り初代は歌にもなっていますけれど、芸のためなら女房を泣かす、という。ところがそこは教えられているのは、芸のためなら女房を泣かす、と、嫁はん泣かす芸人は、ろくな奴がおらん。やはり1人の女を納得させれなくて、なんでお客さんを満足させることができるのか?ということを言うんですな。我々のほうは初代春団治の影響もあり、どうもそっちのほうがふしだらなように思われてるんですよね。あえて言いたくなるんですけど、意外に噺家っていうのは離婚率が低いんです。皆さんよくご存じの噺家はたいてい離婚の体験や経験をしていない方が多いんです。重ねて言いますけど離婚が悪いと言うてるんちゃいますで。ただ世間からは、ふしだらに思われてますからね。その思われてることに対する防御で言うてるんですけどね。
春之輔氏:そうそう。それで、初代春団治がなんせ型破りな方でして。で、二代目が大変苦労をされたんです。それから私の師匠の三代目は、初代とは人生観も落語そのものも180度違う人でしたよね。おっしゃられる通り初代は歌にもなっていますけれど、芸のためなら女房を泣かす、という。ところがそこは教えられているのは、芸のためなら女房を泣かす、と、嫁はん泣かす芸人は、ろくな奴がおらん。やはり1人の女を納得させれなくて、なんでお客さんを満足させることができるのか?ということを言うんですな。我々のほうは初代春団治の影響もあり、どうもそっちのほうがふしだらなように思われてるんですよね。あえて言いたくなるんですけど、意外に噺家っていうのは離婚率が低いんです。皆さんよくご存じの噺家はたいてい離婚の体験や経験をしていない方が多いんです。重ねて言いますけど離婚が悪いと言うてるんちゃいますで。ただ世間からは、ふしだらに思われてますからね。その思われてることに対する防御で言うてるんですけどね。
山本:それで師匠は、上方落語協会の副会長を現在されてますよね。
春之輔氏:文枝会長、それよりも三枝さんでしたけど、その時から副会長としてずっーと会長の一番近くにおります。繁昌亭を作りましたけれど、一の一から知っております。で、繁昌亭が出来たことによって、ある落語ファンは、みんなが落語上手になった、と。それはなんやというと、料理の器が良いと料理は良く見えると。繁昌亭っちゅうのはね落語専門の会場を作ってるんやから、そこで認められへん芸っちゅうのは、それはその噺家が反省せないかんことですよね。確かに器が立派やったら中身が良く見える。
山本:京都の人で言う着道楽みたいな。
春之輔氏:そうですね、それで上等に見えるいうのもありますけどね。噺家の数もおかげで増えまして、繁昌亭さまさまやと。落語の寄席ができたことは、私はほんまに良かったと思うんです。ただ、落語は東京、大阪は漫才やといわれることについてものすごい反発ありましてね。我々から言わしますと漫才も落語も大阪やと。そういう思いもあるんですよ。その中で繁昌亭を作っていただいて。なんせ天神さんの宮司様のご厚意で、土地をただで貸してやるから上の建物は自分らで作りなさいという、このお言葉があってこそですよ。だからできたわけですよ。それまでずっと落語専門の寄席は東京にはいくつもありましたけれど、大阪にはなくなっていたわけで。それは天神さんのおかげですよ。
山本:東京の落語団体と、関西の上方落語協会はどんな風に違うんですか。
春之輔氏:そうですね。東京は落語協会と落語芸術協会と、二つの大きな団体があって、それに対してまた小さなグループがその下にあるんです。ただ関西のほうはね、上方落語協会言いますけど、実は親睦団体でしてね、仲良しの会なんですよ。これ大変難しいんです。つまり噺家はそれぞれのプロダクションである、吉本興業、松竹芸能と、それぞれに人がいますからね。これは東京とはちょっと様子が違いましてね、大変難しいんですわ。で、それまでは友好団体、お友達の会であったわけですけれども、そこで繁昌亭が出来たらそうはいきませんのでね。そういうようなところで、我々はものすごい右往左往したりいろいろ悩んでいるところなんですけど、難しいもんです。
山本:繁昌亭って名前もいいですね。繁盛していくっていう。
春之輔氏:ええ、これは亡くなられた笑福亭松鶴師匠、六代目ですけれども、この方が繁昌亭という名前を千里セルシーのホールの落語会でお使いやったんですよ。で、それを文枝会長がもらえることになった、ということなんです。
山本:今回対談させてもらいたかった一つの理由として、先ほどからお話に出ている4代目の春団治さんを襲名される。これは、僕らのお墓の世界で言うと、家を守っていくっていうことになりますよね。
春之輔氏:なるほど。結局そういうことですわね。ただ東京的発想と大阪的発想というのは、もちろんわれわれ春団治一門というのをこれからも大事にしていきたいです。ただ少しニュアンスが違いまして。私がもし東京で四代目を名乗ったとしたら、みんながおめでとうおめでとうと、当然それに対してご祝儀を頂けると思うんですよね。大阪は、例えば僕が四代目になったんです。例えば山本社長がおめでとう、と。ところが重ねて、いや、四代目なったんです。なら、おめでとう、と。もういっぺん僕が四代目春団治なったんです、というときっと山本社長は、それがどないしたんや、と。大阪的センスはそういうことですよ。
山本:なるほどですね。
春之輔氏:襲名っちゅうことも大事やけども、その本人がどうしたものかということ。その東京的センスと大阪的センスとちょっと違うと。それで東京は歌舞伎のほうもね、十四代目とかそういうのありますけど。大阪は意外に続くことは厳しいと、それは言えると思うんです。あとはやっぱり、師匠が大事でやってきたわけですからね、一門ですからね、これはやっぱり家ですからね。それは当然大事にしなければならないと。それが始まりなんです。
山本:落語と比べたら、先ほどからお話ししていただいている、大阪で言う漫才というのも、師匠、家というのが途絶えていってしまいましたね。
春之輔氏:失礼ながら漫才のほうは、名前を頂いたというのはあるかもしれないですけど、我々は師匠から直接芸を習うわけですよ。だから当然意識は強いですよね。もっとも私は春団治の弟子ですけれども、米朝師匠にも松鶴師匠にも文枝師匠にもお稽古はしていただいてるんです。
山本:それはすごいですね。
春之輔氏:これが一家一門とは言いながら少しニュアンスの違うところで。しかも我々の業界ではお金が一切動かないというのがあるんです。僕が米朝師匠の所へお稽古に行っても一銭の支払いも無いわけなんですよ。もちろんうちの師匠がよその一門を稽古するときもそういうのは無い。もちろん実の師匠と弟子の間にもそんなものはありませんのでね。それがちょっと我々の一種独特の。そやからこそ仲間意識が強いのかもわかりませんけどね。一切お金のことを言わないという。そういう教えを受けてきたからやというわけですけれども。金のことを言うなと。それが特殊な雰囲気なのかもわからないですね。
山本:三代目の春団治さんが師匠で、米朝さんだとか文枝さんだとか、一門の長も含めて親戚みたいなものですね。
春之輔氏:六代目笑福亭松鶴師匠がおっしゃっていたのは、わしらはみんなひとつや、と。僕はそれに共感したんです。それはつまり今の文枝会長もそうであって、それで繁昌亭というものが出来ているんです。皆でひとつや、というのは今の若い人たちに理解してもらえるかどうかわかりませんけど。一門というのはそれぐらい深い仲なんですよ。
山本:そう考えたら、落語の世界での襲名式とか、お寺の世界では晋山式といいますが、本当によく似てますよね。
春之輔氏:やっぱり落語っちゅうのはね、基本はね、仏教ですよ。仏教の精神ですよ。落語の教えというものは。いろいろな宗教ありますけど、基本は絶対に仏教です。もちろん宗教を全面に出して話をすることなんか絶対にないですけれどもね。慈悲や布施や敬うという考え方は、仏教と同じやと思いますよ。
山本:一門を大切にするという考え方があり、現代社会ではそういう風習を閉ざす人も増えました。
春之輔氏:そういうところがわかりませんわね。家族葬とかいうのは寂しいゆうふうに思いますよね。やっぱり、まあ死に花を咲かすとまでは言いませんけれど、やっぱりその亡くなった人を弔うということで、今お通夜がないと、これは寂しいゆうふうに思いますね。そういう風習は残すべきやと思うんですけど。
山本:私もそう思いますね。

春之輔氏:そう思うんですけど、ただ、今使用できる会館が東京やったら九時には閉店いうから帰らなあかん。もうちょっと故人を偲びたいのに、切なく思いますわ。
山本:東京のお通夜ってそうなんですね。いま大阪でも小さいお葬式が増えましたよね。
春之輔氏:それが寂しいゆうことで、夜通し、亡くなった方の前で酒を酌み交わしながら、思い出話をする。これは死者を弔うのに僕は素敵なことやと思いますよ。涙流しながら思い出話をするのももちろん結構ですよね。せやけどそこで亡くなった方が一番好きやったことをそこで話するなんていうのはね、これは大層に言うたら日本人の美徳やと思いますけどね。そういう通夜が少なくなったっていうのは寂しい話ですよね。
山本:落語一門のお通夜とかお葬式とかどんな感じなんですか。
春之輔氏:それはね、それぞれでしたけどね。ある一門では、葬式の喪主が儲かるという噂がたって、喪主争いをしたなんて言う笑い話もありましたわな。
香典のことに関しては、今香典を受けとらないっていう。あれもね、僕は日本人の大した考えで、残された家族を助けるという考え方で、本当に美徳だと思うんです。
山本:確かにそうですよね。
春之輔氏:順番にね、この前助けてもらったから、また次へ、と。僕はそれを何もかも否定するのはおかしい話だと思って。お互いに共同体で、また隣近所の葬式があったらそこ行って香典を。僕はそれがなんでいかんのか、と。なんでかな、と思ったりはするんですけどね。みんなで共同体という意識がいけないのか、それも不思議ですね。
山本:社会のメカニズムがすごく変わっていってるのは事実なんですけどね。
春之輔氏:それはそうですけどね。
山本:師匠のやっている落語と同じで、伝統を守っていかないといけないですね。そういうものは残していってほしいですね。
春之輔氏:僕は葬式そのものを描いた落語っていうのはあんまり知りませんけれども「悔み」っちゅうのは、お通夜行くっちゅう話なんですけれども、やっぱり横のつながりというのが。縦のつながりというのは言えへんけどね。横のつながりということで僕は香典というのは、あればいいんです。なぜそれを皆辞退していくのか、とちょっと疑問に思ったりしますけどね。
山本:またお葬式も形を変えて、いろいろと原点回帰していってほしいなと思いますけどね。
春之輔氏:縁もゆかりもない、お付き合いの葬式だからつらいですわな。これはちょっとどうかという風に思いますけれどね。しかしもっと、基本的な、死者を弔うという、そこを僕は大切にすべきやと思うんですけどね。
山本:そうですね。日本人にとってすごくいいものなので。

春之輔氏:そうですね、やっぱりそう思いますよ。ただ、この間鳥取県の米子でうちの親戚の葬式があって、弟と妹と母親を連れていきましてね。で、これはキリスト教の教会で、大阪から来たから、遠い所から来たからゆうのもありますけど、教会の一番前の所に母親が通されて、で母親が、ええ席やな、と言うたそうなんですよ。芝居見に来たんとちゃうって。まあそれぞれの宗教のやり方があると思うんですけど、日本には仏さんという言葉が大事で、死ねば仏という言い方もありますしね。今仏教の中ではどの宗派と、そういうことは良く知りませんけど、しょうとうするとか、数珠を必ず
手にしていくとか、そんなんは大事なことやと思いますけどね。
山本:そうですね。師匠はお墓についてはどう思いますか。
春之輔氏:実はね。僕の父親と母親、離婚してるんですよ。だからそのお墓というものについてね、まだ母親はおかげで元気ですのでね、いろいろご相談したいことがあるなと思ったりはするんですけど。ただ墓というと、うちの嫁はんが実に穏やかな人間で私のことであらゆることを許してくれる、まあよくできた嫁はんですねん。過去のことを振り返ってですね、いろいろ許してきてくれはったんですけど。ただ、冷静な声でね、私の耳元で、お墓は別よ、って。それが、まあ今の私の悩みといえば悩みですね。冷静にそういいますのでね。
山本:結局一緒になりそうですね。
春之輔氏:いや、それがね。冷静に、お墓は別よ、と事あるごとに言われるんですよ。何とか社長のほうから説得してもらえないものかと。
山本:芸の世界で思い出に残る方はおられますか
春之輔氏:そうですね。結構長いこと可愛がってくれたのは、みやこ蝶々さんですね。蝶々さんは子供さんがいらっしゃらない、いうことで、ものすごい 良くしてくれましてね。一番長い時間2人きりでお話したのは、蝶々さんの箕面のお家で、午前10時半から11時にお伺いして、昼ご飯を頂いて、深夜の2時か2時半ぐらいまで2人っきりで。したがって将棋は2回できるわけですよ。昼間はよろしいんですけど、夜は酒の気配が全くないと。それで蝶々さんは酒は一滴も飲めませんので、僕は、この家には栓をしゅっと抜いたらしゅぱっと泡の出るそんな物は無いんですか?と尋ねましたら、小瓶が出て来て。こんなんぐっと飲んだらおしまいのもんですよ。はっきりいって量が入ってないんですから。またそれも1本だけですか、いうたら、これやさかい私は酒飲み嫌いやねんと。それでちびちびと頂きながらね、お話ししたものですよ。で、話はなんやというと、もちろん堂々巡りになったり、同じこと話してることもあるんですけどね。いままでなんべん蝶々先生のその話を聞いたんやろか、というのもあって。ただ、失礼ながら、まあ合うというのか。それで、お前どうせ暇やろ、というのでお伺いしたんですけど。ほなもう帰りますわ、言うたら、なんやお前帰んのか、そう言うて寂しそうな顔をしはるんですよね。まあもちろんお家に泊めていただいたこともあるんですけどもね。ずいぶん世話になりました。
 山本:もう蝶々さん亡くなられて何年ぐらいなんですかね。
山本:もう蝶々さん亡くなられて何年ぐらいなんですかね。
春之輔氏:それがね、そうやってはっきりせんというのはね、十三回忌、十七回忌とかの知らせが全くないんですよ。
山本:寂しいですね。
春之輔氏:そら寂しいですよ。時々、生玉神社の近くにあるお寺、あの近辺まで行ったらお墓の前で手を合わさせてもらってますけど。そういう行事がなくなってしまうのは寂しいですね。やっぱり十三回忌や十七回忌やそういう節目、節目は大事なことやと思うんです。良い言い方かはわからんけれども、一族郎党のためにもね。そういうのは残していくべきものやと、それは思いますよ。
山本:寂しいですね。本日は本当に色々お話聞かせていただいてありがとうございます。また、襲名の際には駆けつけたいと思っています。
春之輔氏:その節には、2月11日、松竹座という。まだ正式には発表しておりませんけれども、発表しました折にはひとつよろしくお願いいたします。


