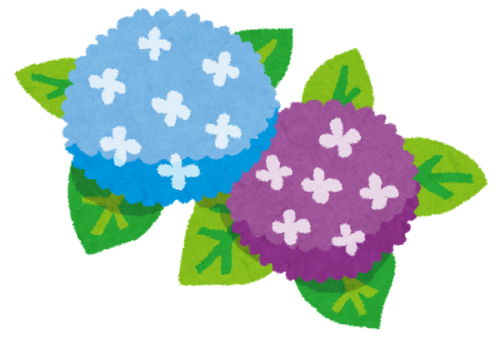なぜお彼岸におはぎを食べる?
投稿日:2025年09月03日
こんにちは、ハピネスパーク交野霊園荻本です。
お彼岸に「おはぎ」を食べるのには、いくつか由来や意味があります。
小豆の魔除け・厄除けの力
おはぎに使う 小豆の赤い色 は、古くから「邪気を祓う力」があると考えられてきました。
そのため、先祖の供養の際に小豆を使った食べ物をお供えし、家族もいただく習慣が根づいたとされています。
収穫への感謝
お彼岸は 春分・秋分 の時期で、農作業の節目でもあります。
春は種まきの時期、秋は収穫の時期にあたり、自然の恵みに感謝する意味も込めてもち米や小豆を使ったおはぎを作り、供えるようになりました。
「ぼたもち」と「おはぎ」の花の由来
春のお彼岸 → 「牡丹(ぼたん)の花」になぞらえて ぼたもち
秋のお彼岸 → 「萩(はぎ)の花」になぞらえて おはぎ
季節の花と結び付けて名前を変えて呼ぶことで、自然とともに生きる日本の風習が反映されています。
ご先祖様とのつながり
お彼岸は「ご先祖様を供養し、感謝する期間」。
昔から 手作りのおはぎを供え、家族で一緒に食べることが供養になる と考えられてきました。
まとめ
おはぎ(ぼたもち)は「魔除け」「自然の恵みへの感謝」「季節の花の象徴」「ご先祖様への供養」という意味が重なった食べ物なんです
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-