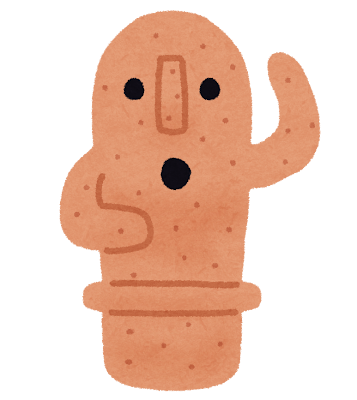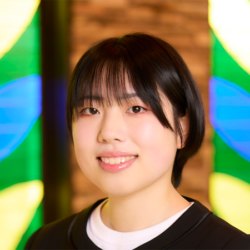古墳時代に終止符を打った大化の改新と「薄葬令(はくそうれい)」
投稿日:2025年08月24日
こんにちは!千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)の中谷です。
今日は飛鳥時代の埋葬方法についてご紹介させていただきます!
大化の薄葬令(はくそうれい)
飛鳥時代の646年、政治改革「大化の改新」の一環として、薄葬令(はくそうれい)と呼ばれる重要な詔(みことのり)が出されました。これは、無駄を省き、質素で統一された埋葬を推進するための法令です。
当時の日本では、各地の有力な豪族が競って巨大な古墳を築き、多くの副葬品を埋葬し、場合によっては生きた人を殉死させるような習慣もありました。これらの慣習は、権力を誇示するものであると同時に、労力や物資を大量に消費し、民衆への負担も大きなものでした。
そこで政府は、古墳の築造を制限し、副葬品の廃止や殉死の禁止など、簡素で平等な葬送文化を国家主導で作ろうと試みたのです。
特に注目されるのが、以下の条文です。
「よろしく一所にさだめて、収め埋めしめよ。けがらわしく、処々に散らし埋むことをえじ。」
これは、「埋葬地は一か所に定めて、そこに納めて埋葬せよ。穢(けが)れをまき散らすように、あちこちにバラバラに埋葬してはならない」という意味です。この一文からも、埋葬のあり方を国家が管理し、秩序だった葬送制度の構築を目指した様子がうかがえます。
この薄葬令は、当時の「祖先崇拝」「権威の象徴」としての墓づくりに一石を投じただけでなく、葬送の合理化と社会秩序の再編成という意義を持ちました。後の律令制度の中にもその精神が受け継がれ、次第に火葬や簡素な埋葬へと形が変化していきます。
現代への名残
現在の日本では、華美な副葬品を入れることは少なくなり、葬儀や埋葬もコンパクトな形式が増えています。時代は大きく変わりましたが、「無駄を省いて本質に向き合う」という薄葬令の思想は、現代の終活や永代供養の考え方にもつながっているのかもしれません。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-