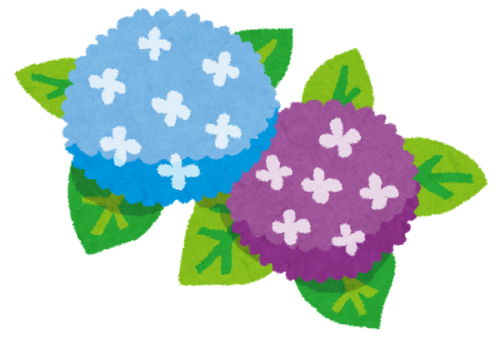大島石のルーツ
投稿日:2025年08月13日
大島石のルーツ(戦国〜江戸時代)
大島石の起源は、戦国時代末期に築城の名手として知られた藤堂高虎の命で築かれた今治城(慶長期)にまでさかのぼる。石積み職人・治衛門が河川より難を逃れて大島へ到着し、そこで良質な花崗岩(後の大島石)を発見し採石を始めたことがルーツとされている。
江戸時代〜明治初期:認知される銘石へ
江戸時代には、すでに美しさと堅牢さに定評のある石として知られていたが、採石技術の限界や搬出困難さから、広く流通することはなかった。明治に入り産業化が進み、1900年代初期には道路や波止場整備によって流通が促進され、全国への販路が開拓された。
昭和以降:墓石材として全国的な地位に
昭和30年代以降、墓石用としての需要が急増し、採石技術も飛躍的に進化。ジェットバーナーなどの機械の導入により採掘効率が向上し、大島石は関西・中四国を中心に「お墓と言えば大島石」とされるほど信頼される銘石となった。
特徴
美しい青みを帯びた色合い、吸水性の低さ、堅牢性といった特質から、墓石のみならず建築材や彫刻材としても高く評価されている。使用実績には赤坂離宮や大阪心斎橋、道後温泉、出雲大社など数々の著名建造物が含まれる。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

南海泉北線光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-