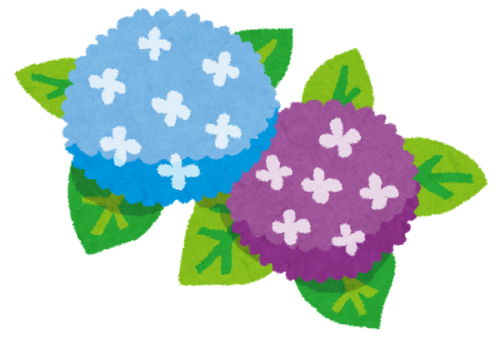文月とは
投稿日:2025年07月23日
「文月(ふみづき)」の由来にはいくつかの説があり、どれも日本の風習や季節感に深く結びついています。以下に、主な説と歴史的背景をわかりやすくご紹介します。
📖 文月(ふみづき)の由来
①【七夕説】=「文を書く月」📜✨
最も有力な説。
七夕(7月7日)に短冊に願いを書いたり、詩歌を詠む「文(ふみ)をしたためる」風習が由来。
平安時代以降の貴族社会では七夕は詩歌や書道の上達を願う行事だったため、「文月」と呼ばれるようになったとされています。
②【稲穂の「穂含み」説】
「文月」は「穂含月(ほふみづき)」が転じたという説。
7月ごろは稲が穂を含み始める時期であり、農業暦としての意味合いが強い。
「ふくむ」→「ふみ」→「文月」と音が変化したとされます。
【書物の整理・読み書きの月】
文を読む・書くことが盛んになる季節、という解釈。
夏の暑さの中、屋内で過ごす時間が増えるため、読書や筆を取る時間が増えるという季節感。
- 文月の歴史的背景
和風月名は中国の影響を受けつつ、日本独自の風習や農作業と結びついて定着しました。
奈良・平安時代にはすでに和歌や漢詩に「文月」という言葉が使われており、季節感の表現として根付いていました。
旧暦の7月(現在の8月中旬頃)は、田の実りや七夕など「実りと願いの季節」として文化的に重要でした。
文月と日本文化
七夕(たなばた)やお盆など、文月には心や祖先に思いをはせる行事が多いのです。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-