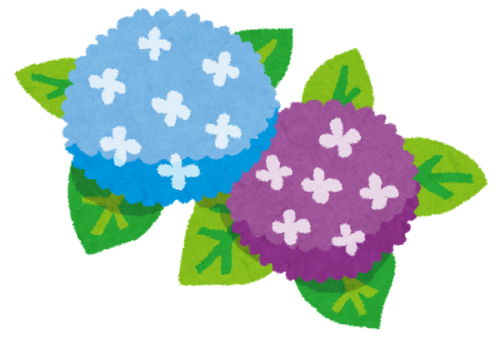大仏の日
投稿日:2025年04月09日
大仏の日と東大寺の大仏
4月9日は「大仏の日」とされています。この日は、奈良の東大寺にある大仏(盧舎那仏)の開眼供養が行われた日(752年)に由来しています。東大寺の大仏は日本を代表する仏像の一つであり、歴史的にも文化的にも重要な存在です。
東大寺の大仏とは?
東大寺の大仏は、正式には「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」と呼ばれ、大乗仏教における宇宙仏を象徴する仏です。大仏の造立は、奈良時代の聖武天皇(在位:724年~749年)の勅命によって進められました。聖武天皇は、国家の安泰と仏教の興隆を願い、この巨大な仏像を造ることを決意しました。
大仏の規模と特徴
東大寺の大仏は、高さ約15メートル、重量は約250トンにも及ぶ巨大な青銅製の仏像です。大仏の鋳造には莫大な資金と労力が必要で、全国から多くの人々が資材を提供し、工事に携わりました。開眼供養は752年に行われ、インド僧・菩提僊那(ぼだいせんな)が導師として儀式を執り行いました。
大仏の歴史的な苦難
東大寺の大仏は、幾度となく天災や戦火に見舞われました。
1180年:平重衡の南都焼討によって東大寺が焼失し、大仏も損傷。
1567年:戦国時代の戦乱で再び大仏殿が焼失。
江戸時代:公慶上人によって再建が進められ、1709年に現在の姿となる。
現在の東大寺と大仏
現在、東大寺の大仏は世界遺産「古都奈良の文化財」の一部として登録され、多くの観光客や参拝者が訪れます。大仏殿は世界最大級の木造建築であり、仏教美術の粋を集めた壮大な空間です。
まとめ
大仏の日に改めて東大寺の大仏を見つめることで、日本の歴史や文化に思いを馳せる機会になります。長い歴史の中で幾多の困難を乗り越えてきた大仏は、日本人の信仰心と努力の象徴とも言えるでしょう。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-