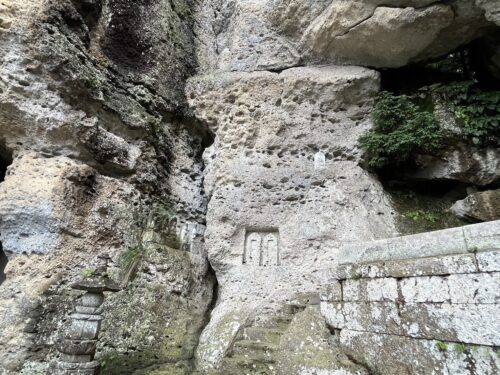酉の市の由来と熊手の意味
投稿日:2025年10月26日
こんにちは。千年オリーブの森京阪奈の中谷です。
商売繁盛を願う風物詩
秋も深まる11月、関東を中心に各地の神社で行われる「酉の市(とりのいち)」。 境内には熊手(くまで)を売る露店が立ち並び、商売繁盛を願う人々でにぎわいます。 華やかなこの行事は、いったいどんな由来を持ち、熊手にはどんな意味が込められているのでしょうか?
酉の市とは?〜起源と歴史〜
酉の市の起源は、江戸時代よりも古い、日本武尊(やまとたけるのみこと)伝説にまでさかのぼります。 日本武尊が戦勝祈願を行ったとされる東京都足立区の大鷲神社(おおとりじんじゃ)が、酉の市発祥の地とも言われています。
毎年11月の酉の日(とりのひ)に行われることから「酉の市」と呼ばれ、 旧暦時代には農民たちが収穫を終えた後、感謝を込めて鷲神社に参詣し、農具や作物を奉納した収穫祭でもありました。
やがて江戸の町人文化と結びつき、「福をかき集める」縁起物として熊手が売られるようになり、 商売繁盛を願う市として今のかたちになっていったのです。
熊手とは?〜なぜ“かき集める”?〜
酉の市で売られている「熊手」は、本来は落ち葉をかき集める農具でした。 これが転じて、商売人たちの間で「運や福、お金、人脈を“かき集める”」という願いが込められ、縁起物として用いられるようになったのです。 熊手には鶴・亀・大判小判・小槌・宝船など、開運のシンボルがぎっしり飾られています。
まとめ
酉の市は、ただのお祭りではなく、季節の節目に「福」を呼び込む日本の伝統文化です。華やかな熊手に込められた想いを知ることで、より一層この行事が身近に感じられるはず。秋の夜、あたたかな提灯の灯りの中で交わされる威勢のいい三本締めに、あなたも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-