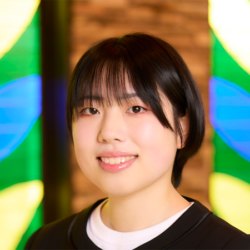お焚き上げという供養の文化
投稿日:2025年11月15日
こんにちは。千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)の中谷です。
朝晩の冷え込みが厳しい季節となってきましたが、体調など崩されませんよう皆さまご自愛くださいませ。
さて本日は、
年末が近づくこの季節、神社やお寺で見かける「お焚き上げ(たきあげ)」という儀式について書いていきたいと思います。
お焚き上げとは?
これは、古くなったお守りやお札、故人の遺品や手紙、写真などを、清らかな火で焼いて“あの世”や“神仏”へと送り届ける、日本ならではの供養の文化です。
起源
お焚き上げの起源ははっきりとはしていませんが、神道と仏教の双方に由来があるとされます。神道では、物には“魂”が宿るとされ、役目を終えた神具をそのまま捨てるのは「不敬(ふけい)」にあたります。仏教でも、故人が大切にしていた品々や経文、遺影などをそのまま扱うのではなく、感謝の念とともに浄火で焼却することで“浄める”という意味が込められています。
こうした「火を通して浄化し、天へ返す」という考え方は、まさに自然との共生と、目に見えないものへの敬意を大切にしてきた日本人の精神文化を表しているといえるでしょう。
お焚き上げに込められた想い
ところで、お焚き上げは単なる“焼却処分”とは異なります。感謝と祈りを込めて、神職や僧侶の立ち会いのもとで丁寧に行われるのが特徴です。そのため、神社やお寺に持ち込む際も、「このお守りにはお世話になりました」「この手紙はずっと手元にありましたが、節目として送り出したい」など、それぞれの想いを込めて納める方も多くいらっしゃいます。
最近では、終活の一環としてお焚き上げを希望する方や、故人の部屋を整理する際に仏壇の位牌や愛用品をお焚き上げで手放すケースも増えています。「ゴミとして捨てるのではなく、きちんと気持ちを込めて別れたい」という現代人の感覚ともマッチしているのかもしれません。
お焚き上げは、感謝と別れを表す美しい文化です。この年末、ご自宅に役目を終えたお守りや思い出の品があれば、一度“手放す供養”を意識してみてはいかがでしょうか。燃やす火の煙にのせて、大切なものをきちんと送り届けることで、心も空間も少し軽くなるかもしれません
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

南海泉北線光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-