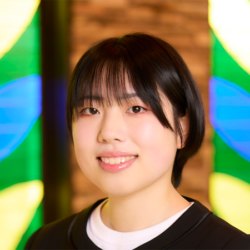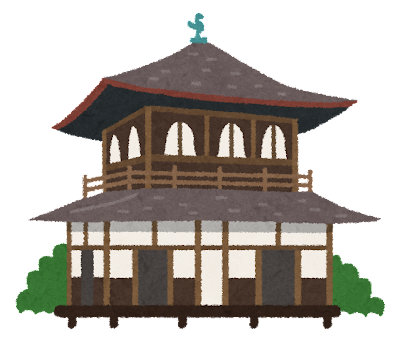七五三の意味・由来とは?
投稿日:2025年10月05日
こんにちは。
千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)の中谷です。
今年は11月15日土曜日が七五三です。
七五三の由来などについて解説していきます。
七五三の本当の意味とは?
神社でのお参りの由来を歴史から紐解く
秋になると、晴れ着をまとった子どもたちと家族が神社を訪れる姿を見かけます。そう、「七五三」です。かわいらしい姿に目を細める方も多いことでしょう。でも、そもそも七五三とはどんな行事なのでしょうか?本当の意味やその由来を、少しだけ深く覗いてみましょう。
七五三は“子どもの通過儀礼”
七五三とは、3歳・5歳・7歳の節目に、子どもの健やかな成長を神様に感謝し、今後の無事を祈願する日本の伝統行事です。
性別によって祝う年齢が異なり、一般的には以下の通りとされています:
3歳(男女):「髪置き(かみおき)」…髪を伸ばし始める年齢
5歳(男の子):「袴着(はかまぎ)」…初めて袴を着る
7歳(女の子):「帯解き(おびとき)」…本仕立ての帯を締める
これらは、かつての「幼児」から「子ども」へ、そして「子ども」から「若者」へと成長する節目の儀式でした。乳幼児の死亡率が高かった時代、無事にここまで成長したことは、家族にとって大きな喜びであり、神に感謝を捧げる重要な意味があったのです。
起源は平安時代・武家の風習から
七五三の原型は、平安時代の貴族社会にさかのぼります。貴族たちは子どもが一定の年齢に達すると、前述の「髪置き」「袴着」「帯解き」といった儀式を個別に行っていました。
その後、江戸時代になると、特に武家社会でこれらの通過儀礼が体系化され、11月15日にまとめて行うようになったとされています。この日は五代将軍・徳川綱吉の長男・徳松の健康を祈って祝った日とも伝えられ、それが庶民の間にも広がっていったのです。
なぜ神社にお参りするの?
七五三で神社にお参りするのは、「氏神様」に感謝し、今後の加護を願うためです。
神道では人の人生の節目節目に神様に祈るという習わしがあり、七五三もそのひとつ。特に産土神(うぶすながみ=土地の神様)への参拝は、地域社会の一員として認められる意味もありました。
また、数え年ではなく満年齢で祝うご家庭も増え、11月15日にこだわらず10月~11月の都合のよい日にお参りするスタイルが主流になりつつあります。
現代の七五三は“家族の絆を深める日”
現代では医療の発達により、かつてほど命の節目を実感することは少なくなりました。それでも、七五三は「生きること」への感謝と、「これからの無事を願う」家族の祈りを表す大切な行事です。
きれいな着物を着て、家族みんなで神社を訪れ、写真を撮って、お祝いの食事を囲む――
そんなひとときが、子どもにとっても親にとっても、かけがえのない思い出になります。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

南海泉北線光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-