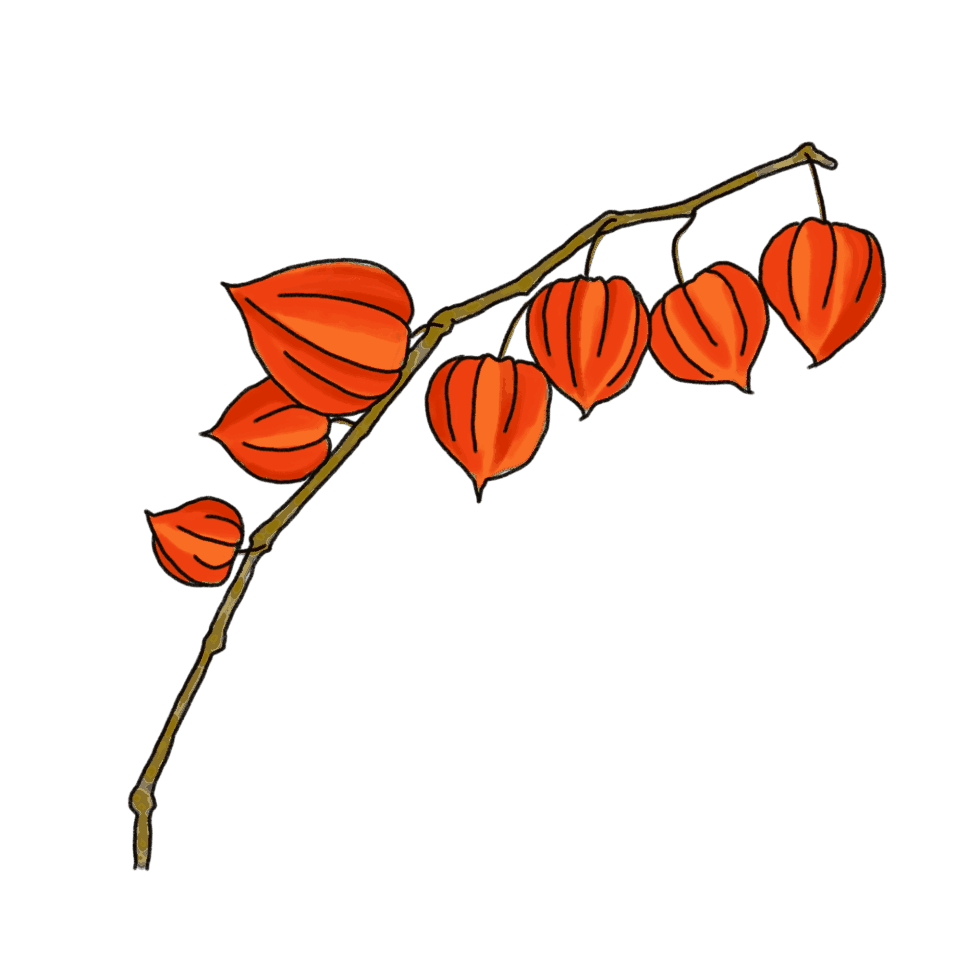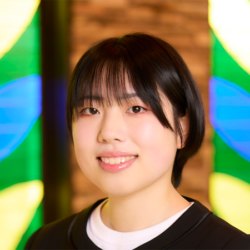お盆と鬼灯(ほおずき)
投稿日:2025年08月03日
こんにちは!
樹木葬・千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)の中谷です。
お盆と鬼灯(ほおずき)──先祖を迎える灯りの象徴
お盆は、日本の夏を代表する仏教行事のひとつです。
ご先祖様や故人の霊をお迎えし、感謝の心を捧げるこの時期は、地域によって7月に行うところと8月に行うところがあります。
一般的には旧暦に合わせた8月の13日から16日にかけて行う地域が多く、「夏の帰省」とも重なり、家族で過ごす大切な時間となっています。
お盆の始まりには「迎え火」を焚き、ご先祖様が迷わず帰って来られるよう道しるべを示します。そしてお盆の終わりには「送り火」を焚き、再びあの世へと送り出します。この“灯り”の役割を担う存在として、昔から親しまれてきたのが「鬼灯(ほおずき)」です。
鬼灯(ほおずき)の由来と意味
鬼灯は、提灯のようにふくらんだ赤い袋状の萼(がく)が特徴の植物です。中には赤い実がひとつ入っており、その姿がまるで灯りをともした提灯のように見えることから「鬼灯(ほおずき)」と呼ばれるようになりました。
「鬼」の字が使われているのは、鬼(霊)の道しるべとなる灯りの意味を込めているとも言われます。また、漢字の「灯」は光を意味し、ご先祖様の霊が迷わないよう導く役割を象徴しています。古くからお盆の飾りとして用いられ、精霊棚(盆棚)に飾られる鬼灯は、まさに“霊を迎える提灯”のような存在です。
お盆飾りとしての鬼灯
お盆になると、仏壇や精霊棚には、精進料理や果物、蓮の葉、キュウリやナスで作った精霊馬などとともに、鬼灯が飾られます。
鬼灯はその鮮やかな赤色と独特の形状で、祭壇を華やかにしつつ、ご先祖様の霊を迎えるための重要な役割を担っています。
地域によっては、お盆市やほおずき市が開かれ、鉢植えや切り花の鬼灯が販売されます。
この時期の鬼灯は、単なる観賞用の花ではなく、お盆という文化と深く結びついた特別な存在なのです。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

南海泉北線光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-