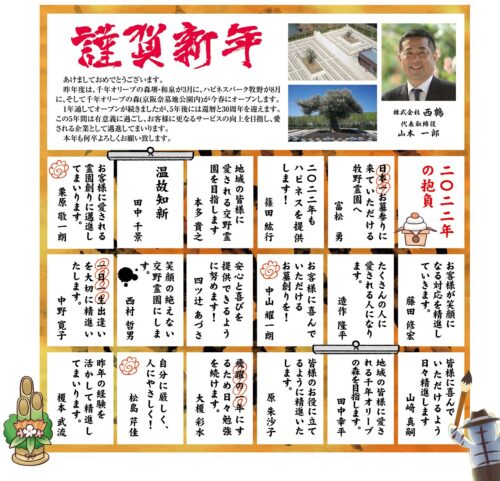海外で亡くなった場合どうすればいい?お骨を海外から日本へ
投稿日:2022年12月23日
こんにちは。ハピネスパーク牧野霊園の松島です。

海外で亡くなった場合どうすればいい?
海外で家族や身近な人が亡くなった場合、日本国内とは異なる手続きが必要になります。現地の法制度や文化の違いもあるため、冷静に対応することが求められます。まずは、以下の流れで手続きを進めていきましょう。
1. 現地での死亡確認と連絡の流れ
海外で日本人の死亡が確認されると、通常、現地の病院や警察が日本大使館や総領事館(在外公館)に連絡を行います。在外公館は、故人のパスポート情報をもとに身元を特定し、日本の外務省へ報告します。その後、外務省を通じて故人の家族へ死亡の連絡が入ります。
2. 現地で行うべき手続き
現地での死亡が確認された後、以下の手続きが必要になります。
身元確認のための渡航
- 基本的に遺族が現地に赴き、故人の身元を確認します。
- もしパスポートがない場合は、日本国内のパスポートセンターで緊急発給が可能です。
- 事前に在外公館へ連絡し、渡航準備を整えましょう。
死亡診断書(死体検案書)の取得
- 現地の医師や監察医から死亡診断書(死体検案書)を取得します。
- これは日本で死亡届を出す際や、遺体搬送の手続きで必須となります。
- 言語が異なるため、日本語訳を用意する必要があります。
在外公館での手続き
- 死亡届の提出:在外公館(日本大使館・領事館)に死亡届を提出し、死亡の事実を公的に記録します。
- 埋葬許可証・遺体証明書の発行:日本での納骨や火葬のために、在外公館でこれらの証明書を取得します。
- 遺体の搬送・火葬に関する相談:日本へ遺体を搬送するか、現地で火葬して遺骨を持ち帰るかを検討します。
3. 在外公館や葬儀社との連携
海外での死亡手続きは、国によって異なります。手続きに不明点がある場合は、在外公館に相談するほか、国際的な葬儀社(遺体搬送サービス)と連携するのがスムーズです。
特に、遺体を日本へ搬送する場合はエンバーミング(防腐処置)が必要なことが多く、現地の葬儀社と連携して手続きを進めることになります。
4. 日本での対応準備
日本国内での手続きとして、死亡届の提出や改葬許可の申請が必要になります。これらの手続きは後の項目で詳しく解説しますが、まずは現地での手続きを確実に進め、遺体または遺骨を日本に移送する準備を整えることが重要です。
遺体を日本へ運送する方法(火葬せずに帰国する場合)
遺体搬送の流れ
1. 現地で必要な書類を取得
遺体を空輸するためには、以下の書類を準備する必要があります。
- 死亡診断書(または死体検案書):現地の医師または監察医が発行
- 遺体証明書:日本の在外公館(大使館・領事館)で発行
- エンバーミング証明書:防腐処理を施したことを証明(エンバーミング処置を行った場合)
- 遺体輸送許可証:現地の当局や航空会社が求める場合あり
- 故人のパスポート:渡航手続きのために必要
2. エンバーミング(防腐処置)を行う
遺体の搬送には、エンバーミング(防腐処置)が必須となる場合がほとんどです。エンバーミングとは、特殊な薬剤を使用して遺体の腐敗を防ぐ処置であり、現地の葬儀社が対応します。
- ドライアイスでは不可:通常の遺体保存とは異なり、飛行機での搬送には防腐処置が必要
- エンバーミング施設のある葬儀社を探す(在外公館や国際葬儀社に相談)
- エンバーミング後に密閉された専用の棺(シーリングコフィン)に納める
3. 航空便の手配と搬送準備
遺体は航空貨物として空輸されるため、事前に航空会社に確認を取る必要があります。
- 航空会社の手続き条件を確認(受け入れ可否・便のスケジュール・輸送条件)
- 空港の貨物セクションに遺体を搬送し、通関手続きを行う
4. 日本到着後の対応
- 遺体は日本の空港の貨物セクションに到着
- 通関手続きを行い、受取人(遺族または葬儀社)が引き取る
- その後、葬儀社の手配により安置所や葬儀会場へ搬送
遺体搬送にかかる費用
遺体を日本へ搬送する場合、以下のような費用が発生します。航空運賃は国や航空会社によって異なりますが、遺体の重量が加算されるため、通常の航空貨物より高額になる傾向があります。
エンバーミング処置 15万〜25万円
遺体専用の棺(シーリングコフィン) 10万〜20万円
航空運賃(遺体の輸送費) 15万〜50万円(距離や航空会社による)
遺体輸送許可証の取得 5万〜10万円
通関手続き・葬儀社の搬送費 10万〜30万円
遺体搬送時の注意点
- 航空会社によって受け入れ可否が異なるため、必ず事前確認が必要
- 国の法規制を確認する
- エンバーミング処置が義務付けられている国もある(防腐処理をしないと輸送できない場合が多い)
- 日本に到着後の手続きをスムーズに進めるため、事前に葬儀社と相談する
遺体を日本へ搬送する場合、防腐処置や書類手続きなど、通常の葬儀とは異なる準備が必要 になります。在外公館や国際葬儀社と連携しながら、スムーズに手続きを進めましょう。
海外で火葬して日本へ遺体を持ち帰る方法
海外で亡くなった方を現地で火葬し、日本へ遺骨を持ち帰る場合には、火葬許可証や死亡証明書の取得、遺骨の持ち込みに関する航空会社・税関の確認が必要 です。国ごとに手続きが異なるため、在外公館(日本大使館・領事館)や葬儀社と連携しながら進めることが大切です。
海外で火葬を行うための手続き
火葬許可証・死亡証明書の取得
- 亡くなった国の自治体や病院で死亡診断書(死体検案書)を取得
- 現地の行政機関または在外公館で火葬許可証を発行してもらう
- 火葬許可証の日本語訳を用意する(行政書士や在外公館で対応可能な場合あり)
火葬の手続き
- 現地の葬儀社や火葬場に依頼し、日程を調整
- 国によっては、火葬を行うための特別な許可が必要な場合もある
遺骨の収納と梱包
- 骨壺を準備し、遺骨を納める(国によっては規定サイズがあるため注意)
- 耐衝撃性のある骨壺ケースや梱包をする(航空輸送時の破損防止のため)
遺骨を日本へ持ち帰るための手続き
必要書類を準備する
- 火葬許可証(または火葬証明書)
- 死亡診断書の日本語訳
- 遺骨証明書(遺体証明書)(在外公館で発行してもらう場合あり)
航空会社への確認と遺骨の持ち込み手続き
- 多くの航空会社では、遺骨を手荷物として機内に持ち込むことが可能
- 事前に航空会社へ確認し、必要な書類を提出
- X線検査で骨壺の中身が確認できるよう、金属製ではなくセラミックや木製の骨壺を使用するとスムーズ
日本の空港到着後の手続き
- 税関での申告が必要な場合あり(空港によって異なる)
- 持ち帰った遺骨は、改葬許可申請を行い、日本の霊園・墓地へ納骨可能
遺骨を持ち帰る際の注意点
- 航空会社ごとに規定が異なるため、必ず事前確認を行う
- X線検査をスムーズに通過するため、透明またはセラミック製の骨壺を使用するのがおすすめ
- 火葬許可証・死亡診断書の日本語訳が必要になるため、事前に準備しておく
海外で火葬を行い遺骨を持ち帰る場合、航空会社の規定を確認し、必要書類を揃えてスムーズに手続きを進めることが重要 です。
日本での納骨手続き(火葬済みの遺骨)
海外で火葬した遺骨を日本で納骨する場合、改葬許可申請 などの手続きを行う必要があります。納骨先によって必要な書類や手順が異なるため、事前に自治体や霊園に確認し、スムーズに進められるよう準備しましょう。
納骨のために必要な手続き
日本で納骨をするには、遺骨の現在の保管場所に基づいて 「改葬許可証」または「火葬許可証」 を提出する必要があります。
火葬許可証で納骨できる場合
一部の霊園では、海外の火葬許可証(日本語訳付き)を提出すれば納骨が可能です。
改葬許可証が必要な場合
一般的な墓地や霊園では、改葬許可証の取得が求められます。
改葬許可証の申請方法
改葬許可証は、現在お骨がある自治体で発行されます。 そのため、遺骨を保管している市区町村で申請を行いましょう。
【改葬許可証の取得手順】
1. 市区町村役場へ改葬許可申請書を提出する
必要書類
- 海外の火葬証明書(原本)
- 火葬証明書の日本語訳
- 納骨先の霊園・墓地の受入証明書(霊園や寺院で発行)
- 申請者の身分証明書(免許証・パスポートなど)
- 死亡証明書(原本、コピーおよび翻訳文)
2. 役所で改葬許可証が発行される(約2週間)
申請が受理されると、役所から改葬許可証が発行されます。
3. 改葬許可証を納骨先の管理者に提出
霊園や寺院へ改葬許可証を提出し、納骨手続きを進めます。
納骨の際の注意点
- 自治体ごとに手続きが異なるため、事前に市区町村役場へ問い合わせる
- 霊園によっては火葬許可証の日本語訳のみで納骨できる場合があるが埋葬許可証も必要とされることが一般的
- 納骨の際には、法要(納骨式)を行うことが一般的
海外で火葬した遺骨を日本で納骨するには、自治体や霊園の規定を確認し、改葬許可証の取得が必要 となる場合があります。
樹木葬霊園での納骨の場合
樹木葬霊園での納骨手続きの流れ
樹木葬霊園に納骨する際の流れは、一般的な墓地とほぼ同じですが、霊園によっては改葬許可証が不要な場合がある ため、事前に確認が必要です。
【納骨の基本的な流れ】
霊園へ納骨の受け入れ確認をする
- 海外で火葬した遺骨が受け入れ可能か確認
- 火葬許可証の日本語訳のみで納骨できるかを確認(改葬許可証が不要な霊園もある)
必要書類を準備する
- 火葬許可証の日本語訳(海外発行のもの)
- 改葬許可証(必要な場合のみ)
- 納骨先の霊園が発行する受入証明書
- 申請者の身分証明書(免許証・パスポートなど)
納骨予約をする
樹木葬霊園では、納骨の際に法要を行うことが多いため、事前に日程を調整する
納骨式を行う(法要の有無は霊園による)
遺骨を霊園の指定区画に埋葬
一般的な墓地との違い
| 比較項目 | 一般的な墓地 | 樹木葬霊園 |
| 納骨の方法 | 石のお墓に納める | 樹木の下や専用区画に埋葬 |
| 必要書類 | 火葬許可証が必須 | 火葬許可証が必須 |
| 墓石の有無 | あり | なし(プレートを設置する場合あり) |
| 維持費 | 年間管理費が必要 | 永代供養付きが多く、管理費不要の霊園もある |
| 供養の方法 | 家族が管理・墓参り | 霊園が管理、合同供養を行う場合が多い |
樹木葬霊園で納骨する際の注意点
- 火葬許可証の日本語訳のみで納骨可能か、霊園に事前確認する
- 一般の墓地と異なり、永代供養付きで管理されることが多い
- プレート設置や法要の有無など、霊園ごとに異なるルールを確認する
樹木葬霊園は、後継者が不要で管理が楽な点がメリット ですが、納骨のルールや必要書類が霊園ごとに異なるため、事前の確認が必須 です。樹木葬について何かお困り事があれば、ぜひハピネスパーク・千年オリーブの森へご相談ください。
まとめ
海外で亡くなった方を日本で供養するには、国ごとに異なる手続きを理解し、適切に進めることが求められます。特に、遺体搬送や火葬後の遺骨の持ち帰りには、関係機関との連携が不可欠です。
こうした手続きは、突然の出来事として直面することが多く、冷静に対応するのが難しいこともあります。しかし、事前に情報を把握し、必要な準備を整えておけば、よりスムーズに進めることができます。
ご遺族にとって負担の少ない方法を選択し、故人を尊重した形で供養できるよう、周囲のサポートを活用しながら慎重に進めていくことが大切です。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

JR学研都市線津田駅から車で3分
-

大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-

南海泉北線光明池駅から車で10分
-

京阪牧野駅から徒歩6分
-

日吉原レジャープールそば
-